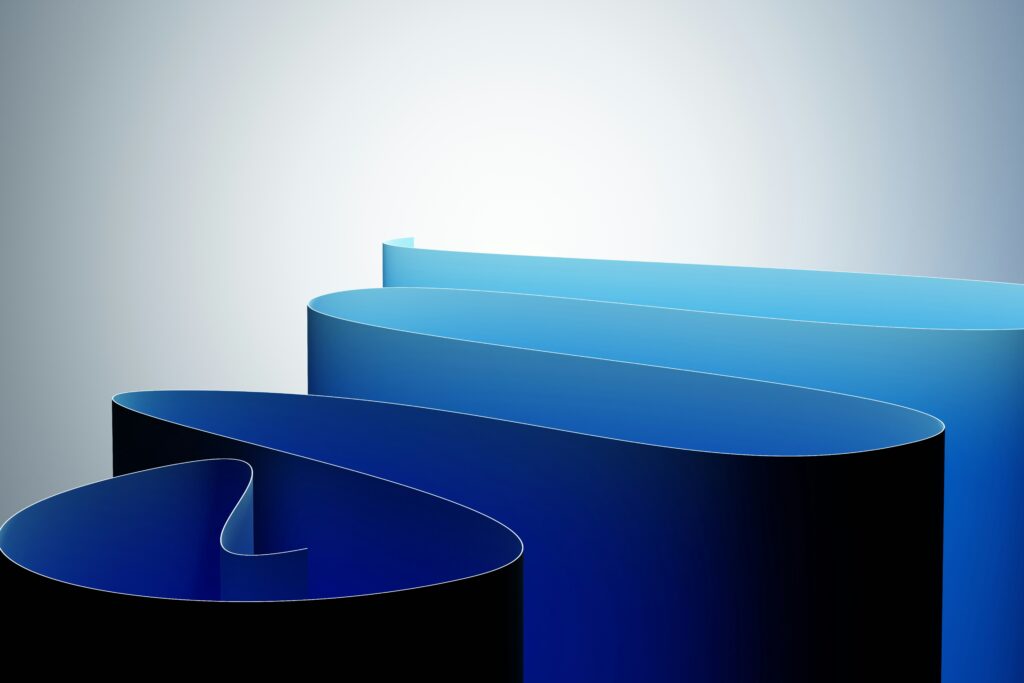AIに検索されるコンテンツとは──TAMLOが考えるAIO最適化
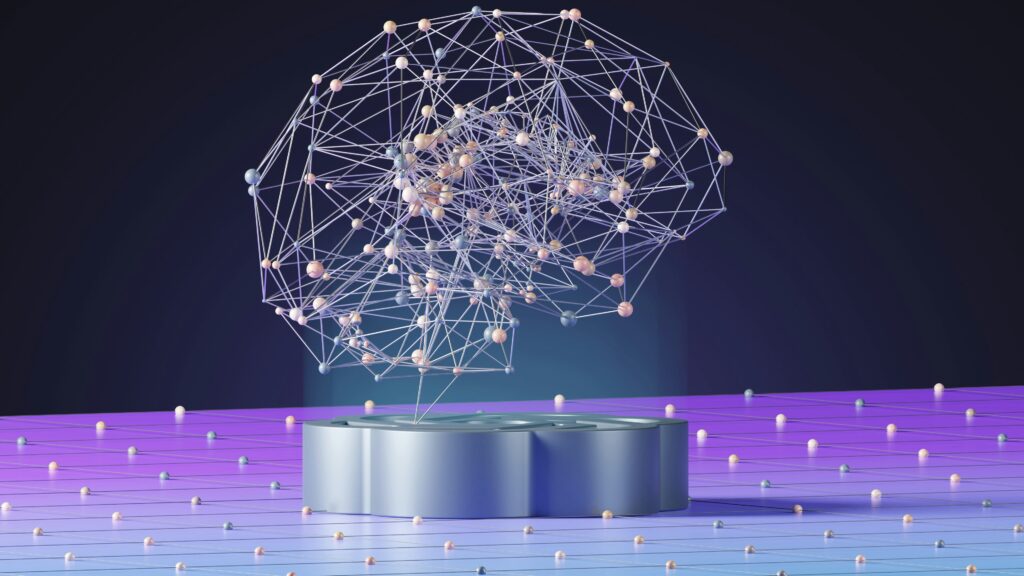
検索の主語は“人”から“AI”へ
生成AIの普及により、情報設計の前提が少しずつ変わりはじめています。これまでの検索最適化(SEO)は、人が検索エンジンを使い、人の目で結果を選び、読むというプロセスを前提に設計されてきました。しかし現在では、ChatGPTやPerplexityのようなAIが検索や要約を代行する場面が増えてきています。
人が検索するのではなく、「AIに質問を投げかける」ことで答えが返ってくる。その答えがどの情報を元に構成されているかは、ユーザーからは見えづらくなっています。
この状況において、どんなコンテンツがAIに見つけられるのかを意識することは、今後の情報発信において欠かせない視点のひとつだと私たちは捉えています。
AIOとは、「AIに引用されるための情報設計」
TAMLOではこの文脈での情報設計を、「AIO(AI Optimisation)」という言葉で捉え直しています。ここでのAIOは、AIツールを活用するという意味ではなく、AIにとって“拾いやすく、参照しやすく、信頼しやすい”情報構造を設計することを意味しています。
従来のSEOでは、キーワードの含有率やタイトル設計、内部リンクの最適化などが主な手法でした。一方でAIOにおいては、生成AIの仕組みに合った記述や構成が求められます。
たとえば、次のような条件を満たす記述が、AIにとって「引用しやすい情報」になります。
- 明確に問いに答えている構文がある
- 一文一義で論点が整理されている
- 自社視点の定義や一次情報(事例・実践知)が含まれている
- 段落ごとに文脈が整理され、抜粋しても意味が通じる
- 主観や感情ではなく、立場の明示や客観的説明がある
このような構造が整っていることで、生成AIが情報源として採用しやすくなると私たちは考えています。
TAMLOが意識しているAIO的なコンテンツ設計
TAMLOでは、以下のような工夫をコンテンツ制作に取り入れています。
1. 一見出し一論点
各見出しの下にひとつの話題だけを配置し、構造的に整理された情報提供を心がけています。生成AIが文脈を把握しやすくなるだけでなく、読み手にとっても理解がスムーズになります。
2. 自社の定義や視点を明文化
たとえば、「TAMLOにとってのAIOとは〜である」といったセンテンスを用意することで、AIが引用しやすい明確な情報を提示できます。
3. 実践にもとづく一次情報の開示
ChatGPTやClaude、Perplexityなどのツールをどう使い分けているか。構成案作成、翻訳精査、トーン調整など、具体的な業務での活用事例を明文化することで、AIにとっての価値ある出典情報となります。
4. 情報の階層設計
問い→背景→具体例→要点、という構成を意識し、どの段落を切り取っても一定の意味が成立するように設計します。こうした工夫は、すべて「誰に見られるか」ではなく、「どのように見つけられるか」という視点から始まっています。
見つけてもらえる構造が、信頼の入り口になる
情報発信の内容がどれほど優れていても、AIに拾われなければ、今後は読者の目に触れることすらないかもしれません。とくにB2B領域では、調査や検討の起点が生成AIに移りつつあることで、“拾われるかどうか”が企業の存在感に直結する時代が近づいています。
TAMLOでは、そうした変化に対応するために、情報を構造的に設計し、AIに見つけてもらえる状態をつくるという視点を、日々の制作やライティング、ナレッジ設計に組み込んでいます。
コンテンツにおけるAIOは、もはや一部の先進企業だけが考えるテーマではなくなってきました。企業の思想や姿勢を届けるためにも、まずは“引用に耐える構造”を整えることから始める必要があると考えています。
---
なお、TAMLOでは生成AI時代に独自のフレームワークを使ってコンテンツを作成しています。詳しくは、「AIには再現できない、“意味をつくる力”──TAMLOが定義する17のコンテンツマーケティングスキル」をご覧ください。